筑後の聖地、久留米水天宮 〜歴史と祈りが織りなす癒しの空間〜
筑後川のほとりに佇む久留米水天宮。水面に映る社殿の姿は、まるで時が止まったかのような神秘的な雰囲気を醸し出しています。今回は、全国水天宮の総本宮として知られるこの神社の魅力をご紹介したいと思います。
悠久の歴史を紡ぐ

水天宮の歴史は、平家物語の哀しい結末と深く結びついています。寿永4年(1185年)、壇ノ浦の戦いで敗れた平家一門。その中で生き延びた按察使局伊勢が、筑後の地に逃れてきたことから物語は始まります。
伊勢は剃髪して千代と名を改め、安徳天皇と平家一門の御霊を慰めるため、この地に祠を建立しました。当初は「尼御前神社」と呼ばれ、地域の人々の信仰を集めていました。その後、慶安3年(1650年)に現在の地に遷座され、久留米藩歴代の庇護を受けながら、今日の姿へと発展してきました。
四季折々の社殿の魅力
境内に一歩足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのが18種もの椿の花々。これは安徳天皇と玉江姫の恋物語にちなんで御神紋となった花です。特に早春には、色とりどりの椿が社殿を彩り、参拝者の目を楽しませてくれます。
生命と安全を守る神様

水天宮は、その名の通り、もともと水にまつわる神様として崇敬されてきました。農業、漁業、航海業者たちの間で信仰を集め、水難除けの神様として知られています。
さらに現代では、安産と子育ての守護神としても広く知られるようになりました。特に安産祈願に訪れる方が多く、その御利益を求めて全国各地から参拝者が訪れています。
春大祭 〜伝統と祈りの5日間〜
毎年5月3日から7日にかけて開催される春大祭は、水天宮の伝統行事の集大成といえます。中でも特筆すべきは、5月3日に執り行われる献茶祭。梅林寺の僧侶と水天宮の神職が共に奉仕する神仏習合の祭典で、表千家不白流のお点前による抹茶が神様に献上されます。
5月4日の御神幸祭では、安徳天皇をはじめとする平家一門の御霊を慰める神事が執り行われ、筑後川の清めの儀式も行われます。5月5日の例大祭では、地元の小学生による「浦安の舞」が奉納され、その清らかな舞いは見る者の心を打ちます。
夏大祭~西日本を代表する筑後川花火大会~
夏大祭は8月5日から7日にかけて開催されます。安徳天皇入水の故事に由来する「水天宮船太鼓」を地域の子供達が奉奏し、その後、船太鼓山車を大石町・瀬下町・京町の3町内を練り歩きます。毎日17時からは大前にて神饌が供され、祝詞が奏上されます。また、8月5日には筑後川花火大会が開催され、西日本を代表する花火大会として久留米の夏の夜を彩ります。
現代に生きる癒しのパワースポット
久留米水天宮は、歴史的な重要性だけでなく、現代を生きる私たちの心の拠り所としても大きな意味を持っています。安産や子育ての守護神として、また人生の節目での参拝地として、多くの人々に愛され続けています。
境内のそこかしこに残る歴史の痕跡、清らかな空気、そして穏やかな筑後川の流れ。訪れる人々は、ここで心の安らぎと新たな力を得ていくのです。

参道が結構長いのでゆっくり楽しめます。
そして、見つけたパワースポットがこれ。

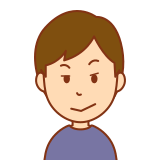
この神社で一番パワーを感じるスポット。
ブレスが出てないのが残念。
アクセス
水天宮の名前道理、筑後川の河畔にあります。
JR久留米駅から徒歩でも行けます。


